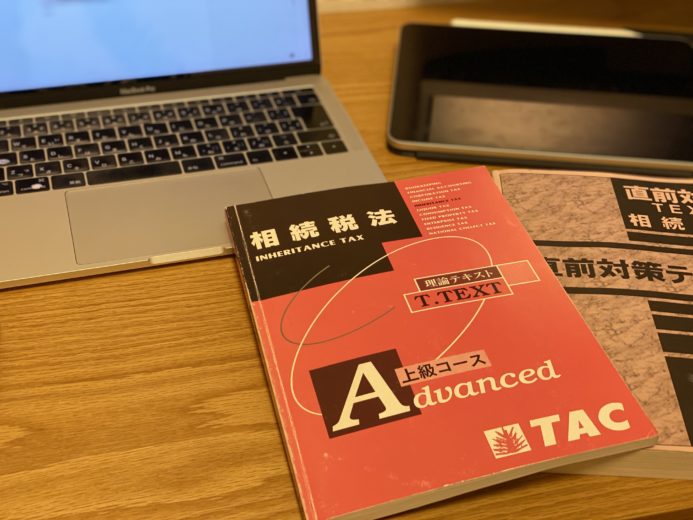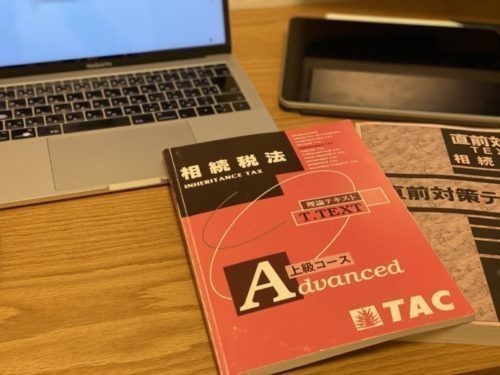税理士試験から10年が過ぎ、独立した現在。その経験は独立後にも知識以外の部分でもいろいろと活かせています。
改めて感じたことをまとめてみました。
税理士試験は苦行である
税理士試験はそれなりに大変な試験。私にとっては苦行とも言えるものでした。
試験を受けて合格するのであれば、11科目の中から5科目を選んで合格しなければいけません。(必ず受験しないといけない科目もあります。)
他にも税理士になるルートはあるのですか、大学院に行くなら、大学院で講義を受け、論文を書かなければいけなかったりします。
公認会計士や弁護士が登録することもできますが、やはり試験はあります。
税務署に勤めている人が税理士になるというルートもありますが、それには23年勤務することが必要です。
どの道を通るかは人それぞれですが、どれもそれなりに大変ではあります。
試験の場合だと、1科目のボリュームが多くて、専念していても3科目が限界。条文(理論)もたくさん暗記しないといけませんし。
5科目合格するには、最短で2年となるわけですが、現実ではなかなか難しく、1年に1科目合格しても5年、働きながらであれば、10年でも早いほうだと言われているのが税理士試験。
実際、私自身もこの税理士試験に専念3年して、仕事しながら1年で、計4年の年月をかけています。
税理士試験で感じたことは独立後にどうつながるか?
税理士試験を振り返ってみて、 税金の知識以外に学んだことも少なくありません。
独立した現在にどうつながっているか?というのも含めて考えてみました。
①崖っぷちを意識 常に真剣勝負
税理士試験にはある種の危機感を持ってのぞんでいました。当時の年齢は29歳。
私の場合、会社を辞めていたこともあり、さすがに中途半端な気持ちでは望めませんでしたし、もし途中でさじを投げるようなことがあれば、「税理士試験を目指すために、仕事を辞めると言ったのはいったい何だったんだ…」ということになります。
それはなんとしても避けなければという崖っぷち感で、のぞみました。
そして2年で合格すると決めていました。科目合格制度というのがあり、ひとつずつ合格していけばいいわけですが、そこにダラダラしてしまうという怖さもあり最短を狙いました。
結果として、前述したように、その倍の4年かかり、最後の1科目は就職して仕事しながらの受験でしたが、合格するまで危機感を持って税理士試験に臨めたのはよかったかなと。
独立後は?
独立してからも、何度か崖っぷちに立つことはありました。
独立当初から、
- 「借りたお金があっという間になくなりそうになる」
- 「あわないお客様と解約できたけど、その代わりに収入に大ダメージ」
- 「事務所の敷金が予定日に入金されずに資金繰りがピンチに」
などといったこともありました。そしてブログにログインできなくなったというようなピンチも。
ただ、そういう崖っぷちでも、もがいた結果なんとかなっています。
ネットを使い始めたのも、ある意味、仕事をとるためも知ってもらわないといけないと、崖っぷちを感じてのことです。
②逃げるという選択
受験では「逃げる」という選択も必要です。
誘惑が敵です。
税理士試験は基本的に朝から晩までずっと勉強でした。そのため誘惑からは逃げるようにしていました。
TV、 ネットなど家に帰れば、甘い誘惑もあります。 そういったものに乗らないように家に帰ってからも計算の総合問題をやったりしていました。
そして直前期。廊下で話していることが多い方もいて、そういったところからも逃げていました。
トイレに行くなら3階のトイレではなく、あえて2階や4階のトイレに行くなどのように。
税理士受験をするならば、時間を奪われてはいけません。

そのためには逃げるというのも戦略の一つです。
独立後は?
現在も逃げるべきだと感じたときは、逃げています。
脱税思考のある方から仕事の依頼が来たとき。 できない仕事の依頼が来たとき、時間を奪われそうな営業、タバコの煙などなど。
③体調管理
受験していたとき、風邪などで休んでしまうとかなり焦りを感じました。体調管理がしっかりできないと、結果的に受験にも影響をきたしてしまいます。
特に本番でお腹を壊してしまうと、これまでの努力も水の泡になる可能性もあり、直前の体調管理には特に気をつけていました。
あと就寝時間も。具体的には6時には起きていましたし、夜も遅くとも23時には寝ていました。
独立後は?
独立した今もやっぱり体調管理は欠かせません。病気になってしまえば仕事をする人がいなくなってしまいます。
そうならないように、気になればすぐに病院に行っていますし、ヨーグルトなど風邪をひきにくくなると言われるようなものは、日々食べています。
④とりあえず行動
税理士試験は毎年8月に実施されます。その後合格発表があるのは12月中旬。 ということは、9月から12月の発表までは、結果がわからなくてモヤモヤする時期があるということです。
さらに、結果が分かったとしても、分かるのは合否だけです(現在は点数はわかる)。
そのように合格してるかどうかわからない、合格しなかったとしてもその理由まではわからないというモヤモヤした中でも、ひとまず前を向いて走り出さないといけないというのが税理士試験です。
独立後は?
独立後もどうなるかわからないけど、とりあえず動いてみるしかないといった場面も多いです。
⑤勉強のパターン
私の税理士受験の勉強パターンは、授業を聞いた後、テキストを1回読んだあとは、ひたすら問題を解いたり、理論を覚えたりと言うものでした。
テキストを読んでいてもそれほど頭に入りませんし、結局はたくさん問題にあたって、アウトプットするのがよかったかなと。
あと、税理士試験というのは、満点を取らないといけないという試験ではなく、中には捨てないといけない問題もあるわけです。
独立後は?
受験で勉強のやり方を学べたことが、今にもいきています。
さらっと勉強したら、まずやってみるようにしていますし、何度も同じことを繰り返しやって身につける、できない仕事は捨てる(やらない)といったことがスキルとして身につきました。
⑥わからない場合の対処方法
税理士試験、ときにはわからないことも出てきます。(というかしょっちゅう)
テキストを見るというのも1つの方法なのでしょうが、テキストは授業後に1読して終わりでアウトプット中心でしたし、読んでもさっぱりわからないということも多いわけです。
そういうとき、講師の方にかなり質問していました。
質問して理解できればそれでいいですし、どうしてもわからなければ、あきらめて捨てようという判断の基準にもしていました。
独立後は?
独立した今でも、わからないことがあれば、コンサルティングを受けて意見を聞いたり、同じテーマの本を数冊読んでというのはやっています。
⑦ライバル
私が税理士試験に合格できた理由の1つには、ライバルがいたというのもあります。
もちろん競争試験なので、基本は全員ライバルなのですが、できる人を数人マークしておくと、直接的な刺激を受けて頑張ることできます。
ライバルの成績をみて、「もっとやらないと」と刺激を受けることもありますし、競う相手がいるからこそ、思った以上のパワーを出せるという効果もあります。
マンガの世界でも
- 翼と日向
- シュナイダーと若林
- キン肉マンとバッファローマン
など、それぞれに刺激を受けて、どんどん強くなっているキャラもいます。
そう考えると、ライバルの存在の重要性がわかります。
とはいえ、普段は気の合う友人の1人だったりします。
独立後は?
独立後でも、気の合う仲間でもあり、刺激をもらえる存在というのは、一定数います。(こっちが勝手にそう見ている)
そういう方々に刺激され、やってみようと思うこともありますし、圧倒的な差を目の当たりにすることもあります。
だからこそ、まだまだじぶんにも伸びしろがあるとも感じることもできるわけです。
⑧休む
税理士受験をする中で学んだのは、休みも必要だということ。
当時は勉強しない時間があると、焦ってしまう気持ちもあったのですが、かといって休みもなく、ただひたすら勉強することがいい結果をもたらすとは限らないということです。
特に1年目の休みというのは、土曜日の夕方のみで、その他の時間はすべて勉強に充てていたのですが、それでも結果として3科目受験して1科目しか合格してなかったりするわけです。
一方でじぶんより勉強時間が少ない人が2科目合格しているという…。
「休む時間も大事で、あえて休むことで頭が整理されるから」と言うアドバイスを講師の方からいただいて、2年目からはそれを実践し、月に1回の日曜日を休みにしました。
結果として、そのアドバイス通りになったわけです。
独立後は?
独立してからも、休みが大事だと言うスタンスは変わりません。ブログを書いたり、日々ややっていることはあるものの、税理士業は 土日祝はやっていません。
休みは休みでやりたいこともありますし。難しいことを考えないことがリラックスにもつながります。
受験で学んだことは独立後の仕事の一部に過ぎない
ある意味時間をかけて、苦労して、多くのものを犠牲にして望んだ税理士試験。
合格できたものの、独立した今となっては、税金の仕事というのは、仕事全体の一部でしかないというのが本音です。
お客様のニーズはそれ以外にもたくさんあったりするわけです。
- 資金繰りをよくしたい
- 節税したい
- 給料はどのくらい払っていいものか?
- 利益はどのくらいでそうか?
- この先どうするか?
- 経理を効率化したい
- 会社をつくりたい メリット・デメリットは?
- 金融機関と上手に交渉したい
- ネットで税金を払いたい
- 経費になるかどうか?
- 会社の株式を事業承継したい
- 相続の相談に乗って欲しい
- ふるさと納税をやってみたい
- 小規模企業共済とiDeCoの違いについて教えて欲しい
- Excelの操作方法
こういったことのほとんどは、残念ながら税理士試験では勉強しないことだったりします。
それでも、こういったニーズの多くは、前述したような税理士受験の経験から学んだノウハウで対応できることも多いです。
まずはじぶんが学び、とにかくやってみる、そして体験を伝えるというように。
現在、税理士試験を受験されている方は減少しているとのことですが、お客様のお役に立てる仕事であることは間違いなく、現在受験されていている方には、「独立してから活きることもいろいろあるよ」ということを知っておいていただければ。
【編集後記】
昨日はオフ。毎日の経理やUiPathの研究をしたあとは、子どもたちと3人で買い物などを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
王将 野菜入りラーメン